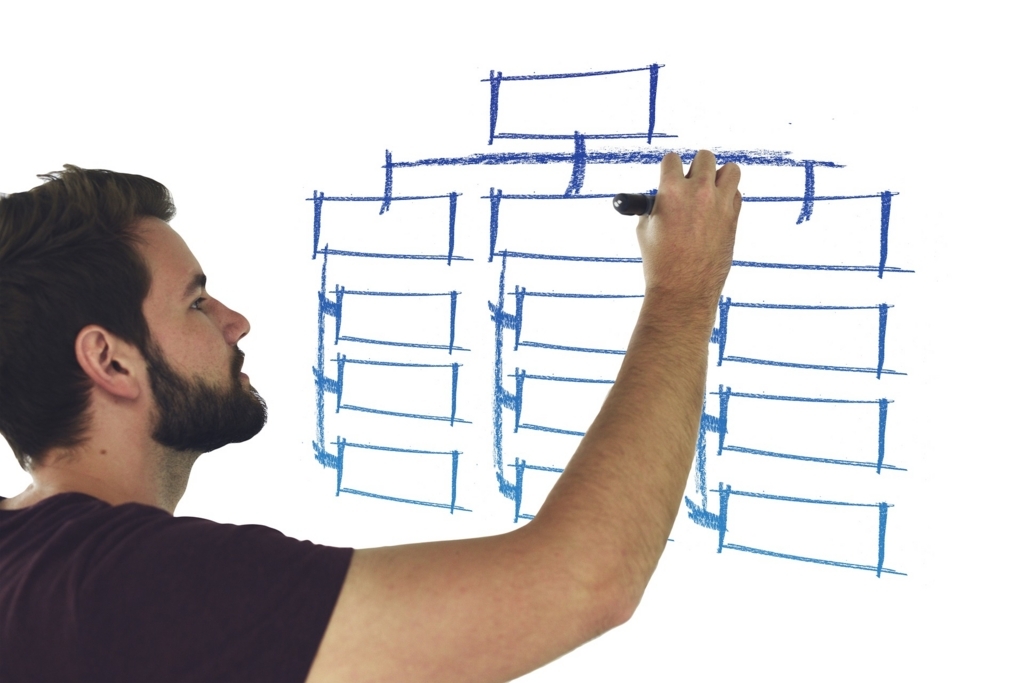
生産性とかって言葉があります。
科学者で言えば、論文だったり、何人博士号の指導をしたりとかなんです。まあぶっちゃけ興味が薄かったんですが、「科学の経済学」という本を読んで、より研究者の生産性にも興味があります。というのも、自分自身が遅速で、中々うだつの上がらない数学者でして笑
で、漁っていた論文には「研究者の生産性と集団(同僚とか)の関係は?」
ってところをたくさん調べていてくれて、目からウロコでした。
研究者の生産性に影響を与える要因とは?
調査はストラスブール(フランス)のルイスパスツール大学(ULP)という大学を1993年から2000年まで観察して行われました。この大学はかなり大きく、ストラスブールの6つのキャンパスには、約18,000人の学生が登録されている17の独立した研究所があるようです。数学、物理学、化学、工学、生物学、医学、そして最後は社会科学と人文科学と多様性にはもってこい。1460人のパーマネント、1,230人の博士課程学生、710人のポスドク、1120人の非研究者(行政スタッフと技術者)が在籍していたもようでこの人たちの論文数を追ったわけです。
この論文数と他の因子を追っていった結果は以下です。
・常勤であることおよび昇進は非常に重要(p=0,01)
やはりこれが一番でした。もちろん逆相関(生産性高い人が常勤なんじゃないの?)
は拭えないものの、まず研究者の身分やら、頑張れば昇進するというインセンティブは社会保障のいいフランスでも大切なんですね。日本も見習ったほうがいい!また、常勤であるかどうかは査読の時の通りやすさにも影響するようです。
・年齢は問題じゃなかった!
これは意外ではありました。一部には、「年齢が上がると、管理者にさせられ、結果論文数が落ちるのでは」という指摘もあります。さもありなん。
・同僚の年齢も昇進も個人の生産性に影響しない。
いやーこれもびっくりでした。こういうのって案外影響受けそうなもんですけれど、これまた有意差はなし。しかしながら、パーマネントでない同僚に限っては、外国人のほうが生産性が上がるとのこと。
・資金調達は重要ではない。
理論研究者の立場から言えばこれは納得。運営交付金のみ少しばかり関係するもののその差は微々たるものだそうです。(常勤0.937に対して交付金−0.003)
まとめ
というわけで今回は科学者の生産性についてのお話でした。まあとりあえず大学は「老害の高給を切って若手を安月給の常勤にし、残りで外国人をポスドクでちょこちょこ入れてく。」というスタンスが良さげ。大学だけでなく会社とかでも同じことがいえそう。ご参考までにどうぞ。
参考
